ここのところ、まち歩きのスナップが楽しくて、135フィルムをよく使っている。
うたろう寫眞
Monochrome Anthology - 暗室系写真サイト - のブログ
2026年1月10日土曜日
在庫という名の安心
ここのところ、まち歩きのスナップが楽しくて、135フィルムをよく使っている。
2026年1月6日火曜日
認識を助けるための、忘却
2026年1月4日日曜日
ノイズに耳を澄まし、目を凝らす
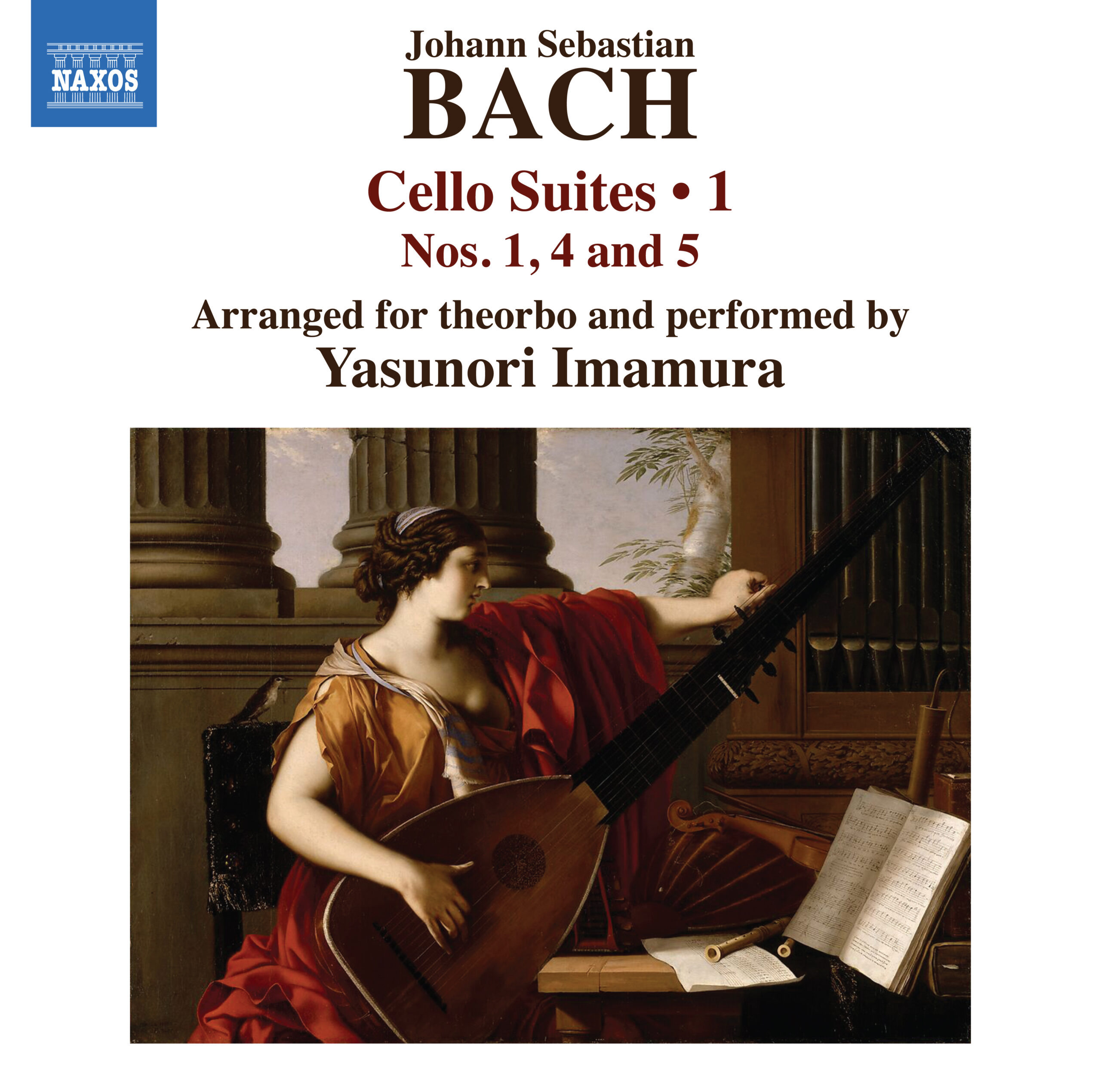
2025年12月29日月曜日
認識の枠とストリートフォトグラフィー
 |
PENTAX SP Super-multi-coated Takumar 55mm f1.8
Fomapan200(EI100) Stoeckler Two-bath Film Developer
SILVERCHROME FLEXGRADE RC Matt
ストリートフォトグラフィーとは、まちを歩き、偶然に現れた現実を即時に撮影したもの、と定義づければよいだろう。
先人たちの巨匠の作品には、人が写っている場合が多く、そこには人間ドラマがあり、いわゆる決定的瞬間が写し取られていた。
二十一世紀に入り、インターネットが普及し、誰もが撮影した画像を公衆の面前に晒すことが可能になった頃から、写真を撮る人々は肖像権に対して、より神経質になっていった。それは、社会全体が「ホワイト化」していく流れとも無関係ではないだろう。
そのような情勢の中で、人が写り込んだ写真を撮影する者は、次第に減少していった。
新聞の三面記事を眺めていると、盗撮で逮捕という報道を頻繁に目にする。こちらにその意図がなかったとしても、いつ自分が犠牲の祭壇にまつり上げられるか分からないと思えば、人を撮ることに慎重になるのも無理はない。
結果として、人が写り込んでいたとしても個人が特定できない状態であったり、撮影対象そのものが都市風景や物体へと移行していった。僕自身も、カメラを提げてまちを歩くときは、自然とそのような撮影スタイルになっている。
PENTAX SP Super-multi-coated Takumar 55mm f1.8
Fomapan200(EI100) Stoeckler Two-bath Film Developer
SILVERCHROME FLEXGRADE RC Matt
カメラという装置を用いてまちを撮影する行為は、絵画などの表現手法とは異なり、「無意識」と直結、もしくはより近い領域で作用しているのではないだろうか。
絵画は、構図や色彩の選択など、理性が介在する余地が大きい。ジャクソン・ポロックは、理性を排除し無意識と接続するためにアクションペインティングという手法を採ったが、それは偶然性に身を委ねたというよりも、理性ではなく無意識によって制御された行為であったと言える。
感性、悟性、理性の順に意識は深まっていくが、ストリートフォトグラフィーは、出会い頭に撮影が完了する表現であり、その多くは感性の領域で完結する。
一方で、風景や静物に取り組む際には、構図や露光時間を吟味するなど、理性の働きが大きく関与する。そこには、写真表現の別の位相が存在している。
ストリートフォトグラフィーは、感性の無意識領域で世界にアクセスする必要がある。そのため、以前のブログに書いたように認識の枠を揺さぶるための内面の再編成、意識的な努力と深い内省が不可欠だと改めて思う。
哲学は、答えではなく問いである。知識ではなく道具である。と、つくづく感じる。
2025年12月27日土曜日
穏やかな執着

現代美術家・村上隆の著書『芸術闘争論』の中で、彼は鑑賞の四要素として次のものを挙げている。
① 構図
② 圧力
③ コンテクスト
④ 個性
この中で、②の「圧力」とは何だろう、と引っかかった。色彩や描かれている事物の強さのことだろうか。
どうもそういう意味ではなく、村上氏はそれを「執着力」や「執念」として説明している。もう少し良くするにはどうすればいいのかを毎日自問自答し、自分の作品を肯定しながら弱点を補完し続ける。その持続力こそが圧力なのだという。
そう言えば、ある美術展の講評で、審査員が「どこまでやり切ったかは、作品を見れば分かる」と話していたことを思い出した。
しかし、執着というものは、方向性を間違えれば、不幸の始まりではないだろうか。
もしその執着や執念の源泉が、「人に見せて評価を得たい」「売らなければならない」「有名になりたい」「人に勝ちたい」といったエゴにあるのだとしたら、それを達成できなかったとき、精神的にも金銭的にも疲弊するだけなのではないか。
もちろん、そうした方向性で制作せざるを得ない立場の人がいることは理解できる。村上氏がそうだとは限らないが。
僕にとって写真は、「余暇を楽しむための活動」、いわばレジャーの一つだ。だから、それらのことは、どちらでもいい。そこには強い執着がない。突き詰めていけば、人に見せなければならないという縛りすらないし、他に何か見つかれば写真を中断することもある。
完成したら、作品をストレージボックスにしまって終わりでもいいし、機会があれば展示してもいいし、どこかの公募展に出品してもいい。
ここであらためて、執着や執念とは何なのかを考えてみた。
僕の場合、向き合うべきなのは、結果から得られる価値への執着ではなく、プロセスそのものに対する精進ではないか、と思う。昨日できなかったことが今日できるようになる。それだけで嬉しいし、それは結果として、緩やかに作品の質にもつながっていく。
何より、そうした姿勢での制作は、フローや純粋経験の状態を生み、幸福に満たされていて、そこに苦しみはない。
そもそも、エゴへの執着が透けて見えるような作品は、鑑賞対象としても、あまり見たいとは思えない。ゴッホやゴーギャンは、執着の末にボロボロになり、最期の時を迎えたが、制作している時間だけは、そうした苦しみから解き放たれていたのだと、僕は思いたい。
僕は、執着を燃やし尽くして何かを残すよりも、執着を手放して、穏やかに生きていたい。そして、そんな在り方がにじむ作品を作れたらいい。
もっとも、これもまた、苦しみから逃れるための一種の執着なのかもしれないが。
2025年12月26日金曜日
捕まった光
2025年12月23日火曜日
印画紙現像液の自家調合
長らく、印画紙現像液には富士フイルムの粉末タイプ**「パピトール」**を愛用していた。使用液8リットル分で400円程度、1リットルあたりのコストは約50円と、非常に経済的であった。
現像液は、印画紙の枚数にかかわらず、作業が終わったその日のうちに廃棄するようにしている。暗室を始めたばかりの頃は、定着液のように説明書の使用枚数に達するまで使ったこともあったが、翌日に持ち越すと液がひどく黄変し、プリントのコントラストが全く出なくなってしまった。これは、現像液の酸化が著しい証拠である。
数年前にパピトールが生産終了となり、富士フイルムのコレクトールEや他社製品も検討したが、いずれも割高に感じた。そこで辿り着いたのが、現像液の自家調合である。パピトールはメトールとハイドロキノンを主薬とするMQタイプの現像液であったため、組成が近い処方を探した。コダックのD-72処方なども候補であったが、誰もが知るありふれた処方よりも、少し変わったものを使う方が楽しいと考えたのだ。
印画紙現像液の処方最終的に採用したのは、**「Agfa 100」**として知られる処方である。
<印画紙現像液 Agfa 100 処方>
水 (50℃) 1500 ml
メトール 6.0 g
無水亜硫酸ナトリウム 78 g
ハイドロキノン 18.0 g
炭酸ナトリウム 150 g (1水塩の場合は175g)
臭化カリウム 6.0 g
水を加えて総量 3000 ml(使用時は1(原液):1(水)に希釈)
※保存は500CCのペットボトル6本
臭化カリウムの増量で温黒調が増すが、効果はそれほど高くないので、僕は、標準量のまま使用している。
僕が元々ネガフィルム用現像液を自家調合していたため、単薬はある程度常備してある。特に使用量が多い無水亜硫酸ナトリウムや炭酸ナトリウムは、写真用ではなく工業用や洗濯用の安価な製品を使用している。写真用の同薬品はなぜか割高なのだ。
この「Agfa 100」処方を自家調合することで、現在でも使用液1リットルを約60円程度に抑えている。僕が液体濃縮タイプではなく、粉末溶解タイプにこだわるのは、コストだけでなく長期保存性の問題もある。粉末の状態であれば劣化の心配がほとんどないからである。
フィルムや印画紙、そして薬品をいかに安定的に安価に入手し続けるかが、サステナブルな写真ライフを実現する鍵となる。カメラやレンズの性能よりも、むしろこちらの方が重要だと考えている。ちなみに、定着液については今のところ自家調合しても市販品より安くはならないため、中外写真薬品の製品を愛用している。定着液の話は、また別の機会にすることとしよう。




